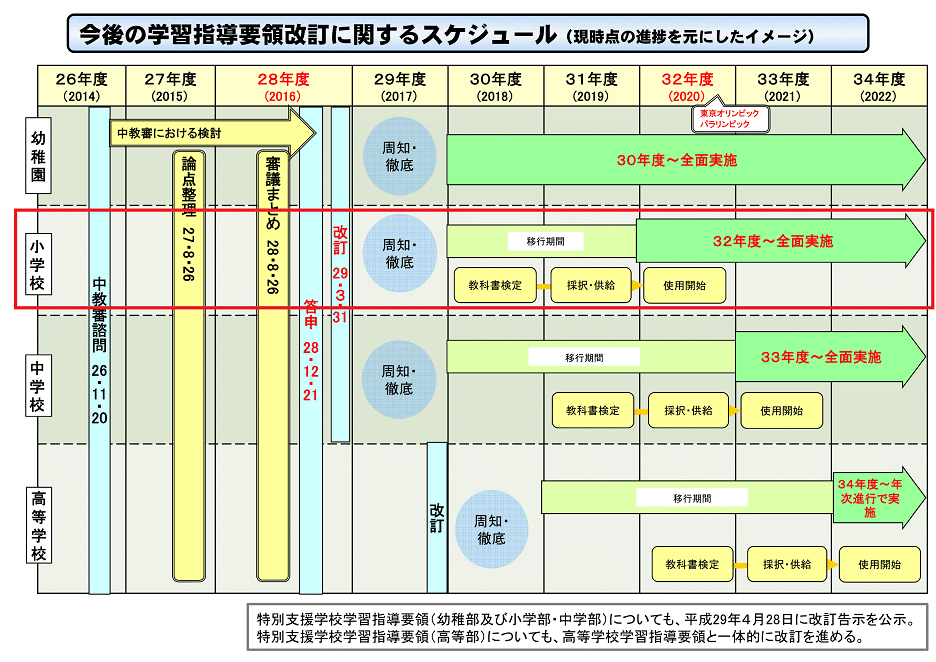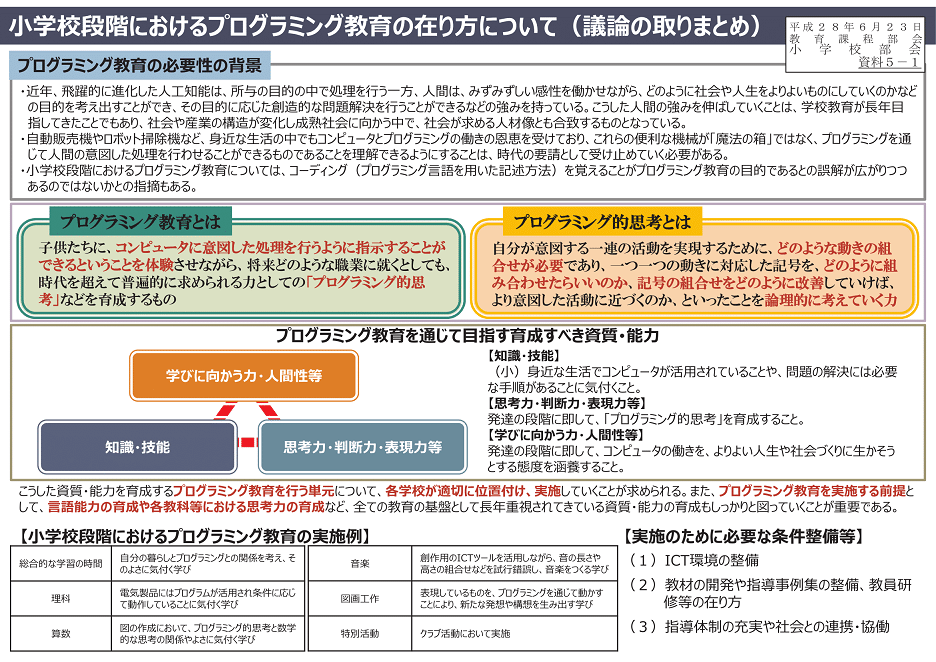「創造力」を広げる
創造力とは?
創造とは、
「新しいものをはじめて作る。」
「オリジナリティのあるものを作る。」
「新しい価値のあるものを作る」
ことをいいます。
プログラミングの学習では、
このような創造力を
ゲームやアプリ、ロボットプログラミングなど
デジタルなモノ作りを通して養い、
広げることができるといえます。
どうやって創造力は養われるのか?
Scratchやレゴマインズストーム
を開発したMITメディアラボの
ミッチェル・レズニック教授が
「クリエイティブ・ラーニング・スパイラル」
という理論を提唱しています。
この理論は、子どもたちの遊びや
学びの過程において創造的であるためには
どのような要素が必要かを示したものです。
レズニック教授は子供たちの遊びを
観察する中で、創造的であるためには
次のようなステップが必要で、
それらはらせん構造になっていることが大切だ
と指摘しています。
例えば子どもがブロックで遊ぶとします。
子どもは最初、何を作ろうかイメージします(想像)
そして、家や車など自分がイメージしたものを
ブロックで作っていきます。(作る)
その後、1人で遊び(遊び)
そのうち、仲間がやってきて一緒に遊びます(共有する)
すると、子どもたちは
「こんな風にしたらもっと面白くなる」
「これはつまらない」
などいろいろな反応を示し、
最初にブロックでモノを作った子どもは、
仲間の反応を取り入れながら、
どうすればもっと遊びが面白くなるか考えます。(振り返る)
このサイクルが何度も繰り返されることで
子どもたちは創造的になると提唱しています。
プログラミングはまさにこの
クリエイティブ・ラーニング・スパイラル
で学べる学習です。
(出典:子どもにプログラミングを学ばせるべき6つの理由 インプレス社)
ロボットプログラミングでは、
ブロックで遊ぶのと同様、
どのように作るかを想像し、
実際にロボットを組み立て、
プログラミング作る。
そして実際に動かし、
みんなに共有する。
もっと、よくするために振り替って、
また想像して、作り直します。
ロボットプログラミングの場合は、
このスパイラルのサイクルが早く循環します。
ロボットプログラミング自体が新しいものを
次から次へと生み出して
共有していける学習環境なのです。
子どもたちはそんな環境の中で、
好きなものを作りながら、
創造力を広げることができるでしょう。